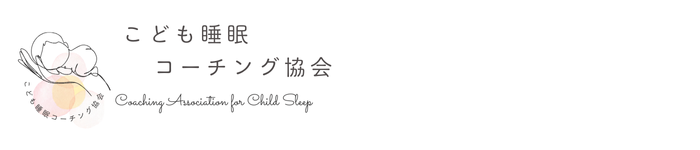岸本 とし子(Toshiko Kishimoto)ニックネーム*もも
合同会社SUILA
所在地:奈良県生駒郡
こども睡眠コーチング協会 代表理事
(Coating Association for Children Sleep)
奈良県出身
看護師
アメリカ心臓協会/日本ACLS協会 BLSインストラクター歴10年以上
2018年~パパママ向け乳幼児の救急講座開講
国立大学看護学科 非常勤講師として勤務
国立大学大学院修士課程にて睡眠研究開始
◇趣味◇
琉球民謡伝統協会 沖縄三線 教師免許
日本フェイスペイント協会 マタニティーペイント認定資格
ママフォトグラファー
海外旅行とダイビング
協会立ち上げの想い
はじめまして、こども睡眠コーチング協会代表理事のももです。
海外では年に数回、ベビーシッターに子どもを託し、夫婦だけでゆっくりとディナーに行くご家庭もたくさんあります。子育てをしながらでも、夫婦だけの時間も大切にしたいという考えや文化からです。私はとても素敵な考えだと思っていますが、日本では様々な面から現実的に難しいと考える方が多いのが現状だと考えています。
海外ではねんねトレーニング文化・ベビーシッター文化が進んでいるため、一人で寝てくれるお子様も多く、寝かしつけの必要もないためベビーシッターに来ていただいて、夫婦で外出することもできます。しかし日本ではまだまだねんねトレーニングが周知されておらず、川の字で寝る文化が定着しています。寝かしつけはパパやママがされているご家庭がほとんどだと思います。
この文化を否定するわけでは全くありませんしスキンシップが図れるという大きなメリットもあります。ですが、パパやママの負担が大きいというデメリットもあることは事実です。私は友人から、『自分の時間が全く持てない』『寝かしつけで一緒に寝ていたら寝落ちして気づいたら朝だった』『旦那さんは寝かしつけできなくで私(ママ)じゃないと寝てくれない』などの悩みを聞くことが非常に多く、知識を得る機会がないために、辛い思いをしているママやパパをたくさん見てきました。
ねんねトレーニング=子供を一人で部屋で泣かせて、寝るまで待つ
というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?実はそれだけではありません。ねんねトレーニングとは、睡眠の質を上げる環境作りや、科学的な根拠をもとにできる有用な方法がたくさんあります。例えば、常夜灯を点けて寝かせていたけれど、真っ暗にすることで夜泣きが改善することもあり、常夜灯を消して眠ることもトレーニングの一環と考えています。そのような小さな対策の積み重ねで、一人で泣かせるトレーニングをしなくともスムーズに寝てくれる、夜泣きがなくなことも期待できます。
睡眠に対する環境作りや対策、ねんねトレーニングのメリットデメリットなどの知識を持って頂いたうえで、◇川の字で寝たい◇一人で寝てくれるようにしたい など、パパやママの納得いく寝かしつけ方法が選択できることが一番パパ・ママ・お子様にとって幸せなことだと思っています。
協会立ち上げのStory

ねんねトレーニングとの出会い
ある日、友人宅に夜ごはんに招待頂いた際、3歳と6歳のお子様が20時になると『Mommy have a good night.』と言って、自室に一人で寝に行ってしまったのです。
あまりにも衝撃的な光景でした。私はまだ子どもはいなかったので、子を持つ友人の情報から
『同室で親子川の字で寝て、母親が寝かしつけをする』
のが当たり前だと思っていました。私自身もそのように育ちました。
別の日に他のママから、やはりお子様全員一人で寝ていて、それは“ねんねトレーニングをした”からだと聞きました。
私にとって初めての“ねんねトレーニング”という言葉との出会いでした。

カナダから帰国後出産し、カナダの友人から伝授してもらったねんねトレーニング法を生後半年になった息子に実践したところ・・・
3週間で完全に一人ねんねが確立しました。毎日19時に一人でスムーズに寝てくれて、19時からは自分の時間ができました。
夜泣きもほとんどなく朝までぐっすり、またお昼寝もしっかりできるようになったので、息子の睡眠に対するストレスは一切ありませんでした。
沖縄三線、アクセサリー作り、マタニティーペイント、一眼レフでママフォトグラファーなど、趣味の勉強や資格取得に時間を注ぐことができました。




一筋縄にはいかなかった息子の睡眠
夫の転勤で関西→新潟県へ
私自身、友人から教えてもらったねんねトレーニング法以外に、睡眠の質を高める環境作りや産後からできる対策など、良い睡眠のベースとなる大切な基礎の知識はその頃ありませんでした。その知識のなさから、このあと大変な経験をすることになるのです…
長男が1歳8か月の時に次男を出産し、長男は赤ちゃん返りで突然一人で寝てくれなくなりました。

☝絵にかいたような赤ちゃん返りをする長男
どう対応してよいか分からず、夫では寝かしつけができず、私が一緒に添い寝をする毎日。そのまま寝落ちをしてしまい、洗い物や洗濯ものの山に、朝から暗い気持ちで起床…。
そして次男は3カ月頃から抱っこで1時間以上かけて寝かしつけた後に、ベッドへ置くと泣き続ける…“背中スイッチ発動”
さらに夜中は1時間毎に起きるようになり添い乳で寝かせる日々…
あんなにスムーズに寝てくれていた長男の寝かしつけにも、ものすごく時間がかかるようになりましたが、夫は出張で帰ってこない日も多く、頼れる人は誰一人居ませんでした。私は一気に二人の寝かしつけや睡眠不足でストレスがかかってしまい、精神的に追い詰められて、めまいや貧血症状など自律神経失調症のような症状が出はじめてしまいました。
いまでこそ、抱っこで寝かせる癖や、添い乳で寝る癖を自分の手でつけてしまっていたと振り返り、どう対応すれば良かったかも理解していますが、知識がないことで子どもの睡眠トラブルに一機に陥ることを実感しました。

次男のねんねトレーニング開始
もう限界を感じていた時に次男が6カ月になり、その頃から日々睡眠の勉強を始め、睡眠に関する研究論文を読みまとめ、まずは夜間断乳の条件がクリアできそうだったのでトレーニングをし、寝室の環境を整え、そして7カ月の時にねんねトレーニングを開始すると…
わずか3日目にしてひとりねんねが確立したのです。
次男の本当に大変にだった寝かしつけも、3日で驚くほど楽になりました。

長男のねんねトレーニング再び…
さて後は長男…2歳を過ぎていたので、時間がかかるかもしれないと覚悟しながら、もう一度2歳からのトレーニング法を実行し、1カ月程経った頃、
長男ももう一度完全にひとりねんねができるようになったのです。

私の辛くてしんどかった寝かしつけ地獄から完全に開放された瞬間でした。
今では二人の息子達は19時を過ぎると自然に眠たくなります。
また、私は毎日20時から自分の時間をたっぷりもてることになりました。
その時間を利用して睡眠の学びをさらに深め、国立大学に勤務する合間に、睡眠に関する研究論文や睡眠に関する書籍をたくさん読みました。さらに大学で一緒に勤務する睡眠の研究をされている先生から協力やアドバイスを頂き、私の協会作りの後押しにもなりました。また、夫とは毎日子どものことや仕事のことなどゆっくり会話をする時間もあります。夫婦の時間をすごく大切にしています。

さてその後三男が産まれました。三男は、産まれる前から環境調整をし、産まれた直後から今まで学んだ知識を活かし、睡眠の質確保や科学的根拠に基づいた安全な環境作りなど、最善の睡眠対策を実施しながら育ててみました。すると…。
睡眠トラブルでほとんど悩まされることなく、また寝かしつけも全くせずにぐっすり眠れる子に育っています。もちろん、体調が悪い時や環境の変化で夜間覚醒や夜泣きをすることもありますが、それも知識をもって対応することで、全くストレスにはなりませんでした。産まれる前から知識を持つことで、一言では言い切れない“こんなにも違うのか‼”と、パパやママ、赤ちゃんの幸せに繋がることを身をもって体験しました。
約7割ものパパやママが子どもの睡眠トラブルに悩まれている現状があるにも関わらず、地域の講座などでも睡眠に関する知識を提供する場はなかなかありません。
私は自身の子どもの睡眠に関する長男と次男の辛い経験があったからこそ、この睡眠の知識をもっとたくさんの、妊娠期におられるパパやママ、お子さまに関わるご職業の方にお届けできるよう普及させ、世の中の子どもの睡眠に関する悩みを解決し、パパやママ自身の自由な時間や夫婦の時間も持っていただけるようにしたいという思いが強くなりました。子どもの睡眠トラブルがなくなれば、ゆっくり自分の時間や夫婦でゆっくり過ごす時間が増え、体や心の余裕のある育児にも繋がります。
何よりパパやママだけでなく子どもが本来持っている眠る力を引き出すことで、成長発達にも多大なる良い影響を与えることがわかっています。
「お子さまが本来持っている”眠る力”を育めるように、心も時間もゆとりのある子育てを導けるように寄り添う」をコンセプトに、正しい知識をもつ仲間を増やしたいとおもっております。
長くなりましたがお読みいただきありがとうございました。もし、お一人でも共感頂き、私と一緒に こども睡眠コーチング協会 認定コーチとして理念を広げ、活動したいと思ってくださる方がみつかりますように。
代表理事 岸本 とし子